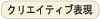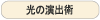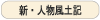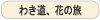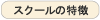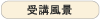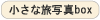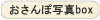|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
“経済大国”日本を縁の下で支え、熟度の高い技能と工夫でモノづくりへのこだわりを忘れない町工場で働く人たち。しかし、世界的な経済不況の影響や日本のお家芸である金型づくりが海外移転される中、仕事を失い、廃業に追い込まれてきているのも町工場。平成21年の「今」、日本の製造業を支えているモノづくり名人達が急速に現場からいなくなってきています。
それでも、他人には真似できない、自分だけの技術を梃子に、したたかに踏ん張り続けている工匠もいます。 東急多摩川線下丸子の駅から数分の住宅街にある、夫婦2人で営む自宅兼工場の赤塚刻印製作所。 6畳一間ほどの作業場に加工用の機械や道具類が所狭しと並んでいます。赤塚さんは、今ではほとんど見られなくなった手彫りで金属刻印をする職人さんです。刻印とは、ハンコのことですが、工業用の場合、タガネと金槌を使って、指の力だけでタガネを押すようにして金属材料を削り、製品番号などの文字や企業のロゴマークなどを彫り上げていく作業のことです。 肉眼では識別不能なミクロサイズのものもあり、眼鏡屋さんが使っていたような拡大鏡を片目に当てて、薄板を剥ぐように削っていきます。 親の仕事を引き継ぎ、キャリアは 40年余。赤塚さんは、その高度な手彫り彫刻技能が認められ、平成16年度の東京都優秀技能者(東京マイスター)に選ばれ、さらに平成20年度の大田区モノづくり優秀技能者としても表彰されています。 今回の小さな旅では、刻印名人赤塚正和さんに、活況だった往時の“町工場時代”のお話などを伺いながら作業風景を撮影取材させていただき、こだわるモノづくりについて理解を深めたいと思います。 赤塚刻印製作所のある東急多摩川線と多摩川に挟まれた下丸子一帯には、かって三菱重工や北辰電気、日本酸素などの大企業の工場があり、機械金属関係の中小零細工場が集中、住宅と工場が混在している地域でした。 ロ 経済環境の変化がこの町にも影響を及ぼし、大企業の工場も多くが移転、町工場は廃業し、その跡地には陸続と大規模マンションが建設され、街の表情は一変してしまいました。新しい時代の様相も写真に捉えてみるいい機会ともいえます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
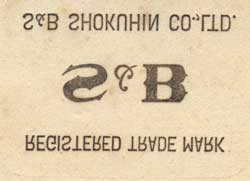 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
||||||||||||||||||||||||||||||||
カリキュラムはフレキシブルに組んでいきます。変更もありますので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ご注意 ご都合のよろしい時にお早めに手続きを済ませてください。 定員になりしだい応募を締切らせていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||